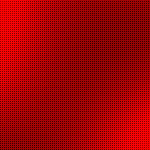「エディプス王の伝説」
昔ギリシャに一人の男がいた。彼の名はオイディプスまたはエディプスといった。彼は父殺しの大罪人として後世にて伝説となっている。しかし今からの話は、その数億年後か、数兆光年後かはわからないが、それと同一の名前を持った、やはりギリシャの地方に生まれたある男の物語である。
「俺は幼少期に親に捨てられて、そして一人でこの人生を彷徨よってきた。まったきの捨て子サウルスだ。神に見捨てられた存在。しかし今最大のチャンスに巡り合えた。それは俺が殺したこの男、お供を連れたじいさん、こいつはある王国の老王だというじゃないか。王をころした俺には、新たなる王になる資格がある。力をもっと力を、それが手に入るかもしれないのだ。」
彼は辻である王国の王を殺した。彼は自分の運命をみつけて、それに殉じることを選んだ。彼はその後、老人の王国を狡智でのっとり、王のお妃(自分よりは10以上年がはなれていた)と結婚し、自分が新王として君臨した。彼は宴会の席で、きまって、ある自慢話をした。
「俺は、昔スフィンクスの謎を解いたことがあるんだよ。あの女の顔をして、獅子の胴体で、鳥の翼をもったやつさ。」
「では陛下は、エジプトまで旅をされたことがあるのですね。しかしどうして、エジプトも征服しなかったんですか。王様ならできたはず。それとも、あそこの大地は広すぎるか、エチオピア人の蛮勇に恐れをなされたのですか?」
返事をしたのは、宮廷の道化である。彼だけはエディプス王に、公然と上のような皮肉をいうことが許されていた。それはエディプスの良心であったのかもしれない。彼は自分が簒奪者であることは忘れていなかった。
「なに、エジプトは化け物がうようよする冥界の国じゃないか。あいつらは、死んだらミイラになって、それで地上に帰ってくるんだ。しかしいったい誰がミイラ女と結婚したいものだろうか。スフィンクスだってそうだ。あいつらは全く文明人だなんていうけれど、実際は獣だよ。灼熱の大地の底に、天国じゃなくて、地獄が眠っていて、底に行くと冥界の王オシリスだのイシスだのに、ぐるぐる巻きにされてしまうのさ。大体俺の魂がマアトの羽よりも軽いなんて誰が信じるかね。だったら俺のほうでも御免こうむるね。俺は勝利の美酒、美女が好きなのだ。力をもっと力を、死よりは生をもっと生を。とそういう主義だから、あそこの陰気くさい雰囲気がどうしても苦手なのさ。」
「しかし、マアトの羽は一枚とは限りませんよ。王様の魂のために、オシリスも、沢山羽を用意して、天秤の片方に載せてくれるかもしれませんよ。」
「おいおい、いつから慈善家になったんだい千鳥足のハンターさん。羽が一枚でないのなら、悪人の魂だって、一個限りじゃないのだから、俺はもう片方の天秤に、俺の心臓の隣に、そういった類の連中の心臓も一緒にのせちゃうね。そうしたら、冥界の羽がいくらあっても足りやしない。
これが、世の中が一向によくならない理由なのさ。しかし俺は結局いやになって、そういう悪人共の魂をかたっぱしからうち殺してしまうだろうな。どうしてかというとな、俺がのる皿は金の皿で、悪人共の皿は灼熱の鉛の皿だからさ。つまり英雄と俗物の差が冥界にもあるらしいのだ。」
「まったくですなあ。しかしイシス神はどうですか?獅子の体に翼の生えたスフィンクスなどは、とてもわがギリシャの人間の美的センスにかなった物ではありませんが、しかし大地母神イシスならば、王様のご趣味にかなうかと思うのですが。」
「は、こいつはあからさまだねえ。しかし俺はこの国の王になるために、あのお妃と結婚したのだ。別に惚れての事じゃない、愛しての事じゃない。年増の女なんて、ああいう地味で可愛げのない女なんて、だれも相手にしやしないからな、俺は慈善事業をやったのさ。
俺は、もっと皆に注目され可愛がられるそんな女がほしいのだ。しかし、どうにも忘れられた女というものに、同情をしてしまうんだな。実際にあのお妃はさんは、お妃と言うだけでお高くとまっているのだが、どうにも哀れな存在なんだ。だって俺が先王をころして、この国をのっとってしまったのだもの。」
「そうですか。しかし王様、男は母親に似た女性を好きになると言いますからね。王様の母親もお妃様のようなかたであったのではないですか?」
「冗談じゃない。俺の母親はもっと派手好きで着飾る女だよ。もちろん俺は孤児で、それをしらないが。しかし夢にそんな女がでてくるのだ。大体いつも波打ち際にでてきて、こちらが頼んでもいないのに、ざぶんと水をかけてきやがる。その時には傷口に塩がしみこむから、痛いのなんのってない。しかも俺が仕返しをしようとすると、その時にはもう遠くの方に波は行ってしまっているんだ。
そういう女が俺の母であることは確信している。着飾る女、美しき女。美がなければ人生は闇だ。酒の神、神秘の神、バッカスの神に誓って、俺はそういう女だけを愛するのだ。
それに比べて妃の地味な事といったらどうだ。あの女は墓場だよ。いや違う、墓場に添えられている花かもしれない。しかし地獄じゃない、極楽にすむ華やかな女ではない。
考えても見ろ、墓参りに行った時に、墓石の脇に小さな花が咲いているだろう。雑草だよ、そういう花を俺は憎々しげに思い、すぐにどけて買ってきた綺麗な花を供えてやるんだ。
それはな、そういう小さな花が、実は高慢でプライドが高い、けっして自分を売り渡さない女だとしっているからだ。
人は綺麗な花を見て、高嶺の花だというが、それは一つの事実だろうな。しかしもっと高嶺の花があって、それは絶対に、自分を売り渡したりしないのだ。
なに、その場でむしり取ってしまえばいいって?
そりゃあ無理だ。だって、その花は売り物じゃないからなあ。摘み取ったって決して自分の花にはなりゃしない。遠くのヒマワリよりも、近くのタンポポとはいうがね、じつは遠くのヒマワリのほうが、容易な部分があるのさ。
考えても見ろ、俺の母親、父親は、そうやって、タンポポのように俺を遠くにやって、そしてそのくせ、今も俺の心のどこかにくすぶってやがる。そしてヒマワリのようにまぶしく思うと、突然に俺の目の前に、顔を突き付けてくるのだ。つまりあいつらは遠くて近い。綺麗な癖に醜い。
だったら、せめて、はじめから遠くにいてくれたほうがいいさ。ただ慎み深いだけのヒマワリならいいのさ。いいや薔薇だね、清らかで、たまにちくりと血を流させるそんな薔薇こそが、俺の心の女性なのだ。
地獄の花だってそうだ。お前らは地獄の花の、その深淵にさく綺麗な花の心こそしらないから、いつでも淫蕩に浸っていられるんだな。まったくお前たちの美を解する心のなさにはあきれてしまうよ。
しかし俺はなにか支離滅裂なことをいっているな。さあもうこの話はやめだ、飲もうじゃないか。」
道化のあからさまな冷やかしを彼は許したし、彼自身も随分陋劣なことを、度々口走った。たまには激昂することもあったが、しかし次の日には忘れていた。そして、宴会が終わると、彼はいつもだれか違う側室のところに行って眠り込んで、妃の元にはほとんどよりつかなかった。
エディプス王が妃と結婚したのは、あくまで王国を簒奪するためであり、それ以外の意図はなかった。彼は妃に魅力を感じてはおらず、むしろ疎んじており、自分の宮殿からも追い出してしまった。これは忠誠心をもった臣下から、恥ずべき行為だと讒言されたが、彼は聞く耳を持たず、そのうち幾人かを見せしめにしてしまった。そのため結局彼女は、宮殿の敷地内の小さな建物に数人の家来と共に、ひっそりと暮らすことになった。
彼女は、妃と言っても、あまりに地味な女だった。豪奢な服を着飾るでもなく、むしろ目を話すとすぐに、家庭の主婦のような地味な格好をしたがるので、誰かが目をつけて、そばにいてやらねばならなかった。
彼女はエディプスよりも10歳以上年上といっても、まだエディプス自身が、20歳そこそこなのだから、見る人からみれば彼女も若者とも言えたかもしれない。しかし地味でおとなしい性質からか、それとも先王の死を悲しんでか、どことなく暗い女であった。
エディプスは、そういう彼女を嫌ったのだが、しかしそれでも、たまに、彼女の元へ赴くことがあった。華美な女たちに嫌気がさして、そうだ例の地味な女でもからかいに行くかと、酔った勢いで、何の悪気もなく彼女を訪ねるのだった。
そういう彼に対して、名目上の夫にたいして、元の夫の仇にたいして、妃は案外に親切な対応をしたし、彼のほうもそういう時はからかうなどという名目はわすれて、打ち解けて話すのだった。
「なあお妃さんよ、どうしてあんたは俺に親切にしてくれるんだい?俺が憎いはずなのに。俺はあんたの夫を殺したのに。とはいっても爺さんだったがな。」
「私はね、あのおじいさん、つまり先王がすきだったわ。でも夫としてではなく、父親のような感覚ね。それを奪った貴方を許すわけがないでしょう。
でもね今の王様、貴方を見ていると、なんだか、とても寂しく泣いているように見えるのよ。まるで誰かを呼ぶかのような。貴方はいつもそんな顔をしているわね。だからつい、少しだけ、優しくしてやろうかとも思うのだわ。」
「そうかなあ。お妃よ、あの道化のやつが、男は母親ににた女性をすきになるというんだ。俺は随分年が離れたあんたを、そういう思いで娶ったのかなあ。」
「まさか。少なくともあなたは私を母親としては見ていないもの。」
「そうだよなあ。でもなぜかたまにだが無性にあんたに会いたくなるのだ。俺はそれだけは、実はあんたを愛していると言える。
でもね、俺が本当に愛しているのは、もっと激しい何かなのだ。激しい力と美なのだ。それがあれば誰にも負けないような何かなのだ。
俺の幼少期が悲惨だったからそう感じるのかもしれないが、とにかく、そういうものを見たり、感じる事こそが、おれにとっては幸せなはずなのだ。きっとそういう道化じみた運命から、俺は生まれているんだ。だからどうかあんたも俺が先王をころしたことを恨まないでほしい。」
エディプス王がこの国を統治し始めて1年。後ろめたくも幸せな日々が続いたが、それも長くはなかった。不思議なことに、だんだんと王国の大地は腐食していき、作物は取れず、そして妃も重い病気に付してしまった。
「どうしてだ。どうしてだ。俺は何も間違ったことはしていない。これは何の呪いなのだ。ゼウスに逆らってバッカスを崇めた祟りだとでもいうのか?いやちがうゼウスだってバッカスだってろくでなしに変わりはしない。すべては幾何学的な説明が可能なはずだ。それが俺の主義なのだ。エウクレイデス式のやつなのだ。」
エディプスは、毎日腐敗した大地をみつめては、その対策に奔走しながら、自分の幼少期のことを思い出していた。やっとだれもが羨む幸せを手に入れたのに、あのころと同じになってしまう。捨てられて、身寄りがなく、みじめで、人からつまはじきにされたあのころに。そんな時代になってしまう。そう彼は恐れた。
なぜなら、大地が腐食したのは、自分が、簒奪者であるからだと、そのせいだという噂が流れていたからだ。どこぞの偉い預言者がそういったらしい。
「みなで俺を追放しようとしている。おなじだ。あのころとおなじだ。捨てないでくれ俺を、俺はもうあの怖い時代には帰りたくない。」
「それは良いことです。しかしそれだけではない。」ある日王室で一人悩みにくれる彼に声をかけたものがあった。
「誰だ、お前はなにものだ。いやお前のことはしっているぞ。俺はかつてお前にあったことがある。そうかお前は昔俺が偉大な英雄になると預言した盲目の預言者だ。あのときは笑い飛ばしたが、しかし今はあんたの言う通り、俺は王になった。」
現われたのは、ぼろきれをまとった盲目の老預言者だった。実は大地の腐食をエディプスの呪いのせいだと予言したのも彼だった。
「私は、忠告にきました。」
「なんの忠告だ。いやしかしこれはありがたい。どうかこの大地の腐食を止めるすべがあるのなら、教えてほしい。」
「いえ私は預言者ですので、それは無理です。私にはこの呪いは止められないものだとしか、そうとしか言えません。」
「・・・・・そうか、所詮貴様もその通りの預言者風情か。なぜ預言者風情などというか、恩人になぜそのような言い方をするか、貴様はわかるか。今や王国はしにたえつつある。その現実が、変えられないのなら、預言など何の意味もない。
王国もそうだし、妃も病で死になんなんとしているのだ。俺は医者に妃の病をなんとかなおしてくれるように、それなりの金をはらった。しかし医者のやつは、病は治せても、死神には、勝ち目がないとそう言いおった。自分のふところは膨らませているのに、表だけお悔やみを申し上げるというわけだ。
わざわざ俺の前にしゃしゃりでて、そんな不幸な予言をするのなら、お前もやぶ医者と変わらない。ようするに、俺の呪いのせいで、俺が王国を簒奪したせいで、先祖の霊がたたって大地が腐食したなどというのだろう。
それともお前は来世や冥界の話でもしてくれるというのか。冥界で死んだ者達と再会できるとそういうのか。骸骨どうしで、包帯グルグルミイラどうしで。いやそれとも綺麗な体のままか、そうならば、まあいいさ。そうならば、まだましさ。」
「なぜましです?もし死んだものともう一度あえるのなら、これ以上の幸せはないはずです。」
「お前は預言者なのに馬鹿だよ。大馬鹿だ。本当に大切なのは、死んだ人じゃない。生きていた人じゃない。」
この言葉を聞いて、預言者は、エディプスに全てを、少なくとも彼の知っていることを、打ち分ける決意をした。
「私はたしかに大馬鹿です。なんといってももう80年このかたぼろをまとって彷徨いながら、真理を探究し続けて、そのくせなーんにもわからなかったのだから。
しかし今のところそれは貴方も同じですぞ。いいですかもうすぐ貴方のお妃、一年しか、いえもっとわずかにしか、いっしょにいなかった、一度も心すらまじわらなかったあの女性が死に絶えようとしています。しかし貴方は、王国の事ばかり心配して、そこから目をそらしているのです。私にはそれが歯がゆいのです。
貴方は、自分の父をころして、その王国をのっとったのです。そしてその妃と、自分の母親と結婚しようとしました。しかし貴方にはそれが怖いのです。貴方は心のどこかで途中から、気が付いていました。しかしそれを認めるのが怖いのです。私は盲目ゆえ、このことをしっておるのです。貴方はお妃を愛しているのです。」
その言葉を聞いて、エディプスは雷に打たれたように固まってしまった。自分の父を殺して母と交わったというその言葉を聞いて。
「俺が父を殺した? あの俺が殺した男が父。それを俺は知らなかった・・・・いや気が付いていたのか、なんという道化だ。栄華を達成したはずが、なんという道化だ。
しかも母親と結婚していただなんて、それは許されざる罪悪だ。しかしこんな侮辱があるだろうか、これは運命神のいたずらか、それとも俺に自由な意思があってそうしたのだろうか?なあ預言者よ、いったいどっちなんだ。俺は悪人なのか、それともただの可哀そうな男なのか。いや俺は英雄なはずだ。」
「今貴方の愛した人が、死にかけております。そこに駆け付けなさい。それだけが、貴方に出来ることのはずです。そして自分の運命をしっかりと見つめるのです。貴方がこの国を去らねば、もう大地は蘇らない。」
「それは、俺に王をやめろと言うことか。この俺が王でなくなれば、後に残るのは、父親をころして母と交わった、そんな罪人が一人出来上がるだけだ。そうすれば、俺は一生後ろ指を指されて生きなければならない。またあのころに逆戻りだ。捨てられて誰もそばにいないあのころに。
エディプス王か、ただの道化で罪人のエディプスか、もし後者が俺の運命だとしたら、それは不当だ。どうして俺なんだ、どうしてお前らじゃない。お前だったら選べるか、そんな辛い道を、選べるのか。いやこれは自分でこんな道を、選んでいると言えるのか。人生とはなんだ!」
「それは貴方達だけの運命です。今あなたが、豪奢な服を纏い、私が盲目でぼろをまとっているのも、私達だけの運命です。
私がいるのも貴方のおかげで、貴方がいるのも私のおかげです。どんな憎むべき人間も運命も全て一蓮托生です。これは因果法則よりも輪廻転生よりもたしかな運命神の教えです。私にはそれしか言えることがない。それを正義だとも悪だとも断言できない。ただ貴方は、自分の運命から逃げてはいけない。これは正義の問題で、自由意志の問題などではないのです。」
預言者がそう言い終わるやなや、エディプスは駆け出した。妃が伏している部屋に向けて走った。
しかし実に一直線というわけにはいかなかった。大体最後に預言者がいった正義というのが、気に入らなかった。運命はなるように元のさやに納まるという運命神の正義。人の不正をだだして、運命への抵抗をしいたげて、全てを平らにしてしまう正義。それに彼はしたがったわけではなかった。
彼はあるところまで来ると急に引き換えし、このままどこか、遠いところに行ってしまおうかとも思いはじめた。たとえばこのまま華やかな女性達のところにいって、死にひんしている地味なだけの妃など忘れてしまおう。
俺は妃を愛してはいない、惹かれてはいない。俺は綺麗な花がすきなのだ。華やかで、うっとりするような。だったらそこへ行けばいい。しかし、今俺はそこに行くことはゆるされない。花は売り物ではないのだから、妃の死体を硬貨にして女にあいに行くことは、今の俺にはできない。
このままどの道をたどっても、どうせ大地が丸いのなら、おなじことで、運命からは逃れられないのかもしれない。全ての道はつながっていて、逃げてもそこに舞い戻るのかもしれない、このなんどとなく歩いた城の廊下も、今では無限回廊の様だ。
彼はひとりで、ランニングをしているかのように、廊下を行ったり来たり、し始めていた。行くべきか行かざるべきか。おそらくはこの時、彼は一生分の廊下を走ったであろう。その位長い時間彼は永劫の転回をしているように思えた。それをみた臣下達は、彼に話しかけるでもなく、平伏しながら気の毒がった。
「何が運命神だ。ましてや因果だの輪廻転生だとさ。もしそんなものがあるのなら、俺のこの道化ぶりも未来永劫永遠にきざまれることになるんだ。あの世でも笑い者じゃないか。そこにどんな救いがあるというのだ。まったく、あの爺さんのような迷信家達の無神経さには反吐が出る。お前らだけがかってに生まれ変わっていればいいんだ。俺は一人で神を呪ってやる。」
そういいながらも、彼は少しずつ一応、妃の元にむかっていたのであり、気が付くと王宮の外にまででていた。しかしそれでも、彼は最後の最後まで、決心がつかずに、この後自分でもどうするのか、まるで見当がつかなかった。
さらに言うと、この無限の時間の中で、まさに無限の時間があるのだから、様々なくだらないことが、彼の頭をかすめていった。それはたとえば、廊下を歩く際には、周りにいけてある花や草の枚数や、土の色や、なぜか肥料として土に紛れ込んでいた焼き魚の骨や、カーペットがめくれていることだったり、そしてそういうことと一緒に、たえず頭の中で、色々な観念的な疑問も湧いてくるのだった。
「俺はマアトの羽の天秤の反対には、魂がのると言ったけれど、しかし心臓がのるとも言ったな。あれはどっちなんだ。魂が心臓なのか、心臓が魂なのか。いやそうじゃない。今俺は頭で考えているのだ。頭が魂なのか。つまり精神と肉体、瞑想的な精神、数学やら幾何学やら、そういう瞑想的な学問と、そうでない、オルフィック教のような熱狂があるのだ。しかしどっちみち結局は真理にいきつくわけで、そしたら俺は破滅しちゃうのだ。
しかし、因果応報なんてクソくらえだ!この俺の前世が呪われていたから、こんな目にあうのだとして、またぞろこんな呪いをうけて、親殺しをして、それじゃあ一生何もかわら無いじゃないか。親父の悪行の報いなら、なにも俺にかかることはない。もしこれが試練だというのなら、なにも前世や未来は教えてくれなくてもいい、しかし自由意志の根拠、人間の設計書だけは、少しは教えておいてほしいね。いやむしろ神はまったく不完全な人間などをはじめから創らなければよかったのだ。
それに、俺に殺された人間達はそう悪いやつらじゃなかった。しかしあいつらの方が先に死んだじゃないか。むごたらしく死んだじゃないか。神さま、あんたの天秤はいかれますぜ。
そうさ、神様の天秤はいかれてる。この世は神のうつし世で、天上界に、理想的な天秤の元型、ええとたしか、そうプラトーンのイデアがあって、それがいかれているらしい。だったら地上の天秤がみな不完全なのも道理だね。でもって、天上世界には、完全な親殺しのイデアも存在するわけだ。しかしこれはくだらない戯言だ。」
こんなことを延々と考えながら、あいかわらず行ったり来たりしていたエディプスだったが、そこに、色とりどりの小鳥たちの、楽しそうな歌声、ささやき声が聞こえてきた。
「父を殺したエディプス王。母とまじわる大罪に、嘆き悲しみ両目をえぐる。生まれて来なきゃよかったと、早く死なねばならないと、嘆き悲しみ、両目をえぐる。ぐーるぐる。運命神のてのひらで、しかり、しかりとぐーるぐる。ご満悦だよぐーるぐる。」
エディプス王は、その鳥どもに石を力いっぱい投げつけて、追い払った。そしてその後我に返ったかのように、あたりを見回した。
「ふむ、今日は曇りか。」
そう言ったが早いか、彼は妃の元に全速力でかけていった。鳥たちの嘲りに意地になっていたのかもしれない、いまだ心はきまってはいない、しかし、それでも彼は妃の元に行かなければならない気がした。
そのころ、妃は、も言う治る見込みがないと、医者もさじを投げ、わずかな者達がせわをしていた。部屋自体は、豪奢な物であったが、死の影により、寂しいものとなっていた。
エディプスは駆けつけると、わずかな看病人、妃を最後までしたい続けた人々を、しりぞけて、妃と話をすることにした。わずかな看病人たちはエディプスをあまりよくおもってはいないだろうから。
「妃よ大丈夫か。いや返事はしなくともいいが、聞いてくれ。俺はおろかだった、俺は自分の父をころしたのだ。自分の中の英雄をころしたのだ。そして国を乗っ取たのだ。こんな馬鹿な話があるか。
俺は自分の道をまっすぐに駆け抜けて来たとおもっていたのだ。しかし気が付けば、それはぐるぐると同じところをまわっていただけなのだ。いつも同じ波がくるのだ。これは道化の物語だ。俺は道化だ。なあおい妃さん、貴方は俺の母親なのかい、そうなんだろう?」
エディプスは覚悟をきめた。自分の母親と結婚してしまった、その罪悪を少しだけ受け入れる覚悟を。しかし帰ってきたのは、まったく予想外な答えであった。
「いいえ、ちがうわ。私は貴方の母親ではないし、波でもないわ。私は貴方の母がしんでから、先王の妃になったのよ。私は二代目なのよ。それは貴方だって知っているはずよ。だから、あなたが私の息子なはずがないわ。」
それはエディプスに、再びショックを与えた。彼は、自分の波が、夢に出てくるものが、彼女であればいいし、むしろ彼女であるとしたら、屈辱であるとかんじていた。もうこの時には、こういう時には、運命と屈辱と絶望をあじわってやろうと、その一心でここまではってきたのだ。しかし彼女は、自分の波ではなかった、しかしそれは当然だ。たしかに言われてみれば、彼もいつか臣下から妃の素性を聞いたことがあった。彼はそれを忘れていた。意識したこともなかった。
それに、もし自分の波なら、いつも自分を遠ざけて、傷つけたあの人なら、そのくせ急にやってくるあの人なら、きっともっと激しくて、華やかな性質を持っているはずなのだ。妃は、自分の母ではない。
「ねえ覚えておいて。もし人生が物語で、私が悲劇のヒロインみたいに扱われたのだとしら、貴方が私を冷遇された捨てられた存在だと思っているのなら、それは最大の侮辱よ。私はそういう作者を許さないわ。」
「・・・・・なぜです。人は皆英雄になりたいし、それか悲劇のヒロインでも悪くないでしょう。」エディプスはうつろな目でかろうじてそういった。
「そうだわ。私もなれることなら、英雄になりたいし、いいえ悲劇のヒロインにこそなりたいわ。でもそれでもね、同情されるのはごめんだわ。貴方は私を憐れんでいるのでしょう。死にゆく私を。あなたが一度も惚れる事の出来なかった可哀そうな地味な女を。」
「いやそうじゃない。そうではない。俺は貴方に一度くらいは惚れたはずだ。第一なんであんたは、俺に優しくしてくれる?いや俺は知っている、それはプライドのためなのだ。憎しみのためなのだ。あんたは誰にも自分を売りやしない。そういう女は、あんたは時に、美さえもにくんで、美に奉仕することもにくんで、それで綺麗な着物も脱ぎ棄ててしまう。」
「かってなことをいうのね。私はね、お妃だなんて、捨てられた女だなんて、病気で不幸にも死んだなんて、そういう風に言われるのが嫌なだけよ。私はだだの女。立派に生きて立派に死ぬ。英雄ではなくとも、私はその誇りだけは、大切にしたいとおもっているのよ。」
「しかし、誇りなんて何の役に立つ。英雄か死か、それが俺の人生なのだ。もし英雄でなくなれば、みなそっぽをむいてしまう。それこそ誇りではなくて、塵芥のほこりだ。華やかな女も、臣民も、それどころか、やつらは、俺に石を投げつけてくるだろう。俺は破滅したんだ。誇りがなんになる。あんたは綺麗ごとをいっているだけだ。正義だの運命神だの、道徳だの、そういうことで、一体何の得になるというんだ。あんたはやはり俺を憎んでいるのだ。それも当然だ。俺は憎むべき父殺しなのだ。」
「そうね。でも皆が言う道徳とか倫理なんてクソくらえだわ。そんなもの私はいらないわ。貴方はそんなものがほしいの?まあ気持ちはわからなくはないわ。」
「どうして、しかし、それがなければ人間はやっていけないじゃないか。あんたが誇りといったのではないか。この哀れな俺を、道化の俺を、救うために、気休めで誇りなどといったのではないのか。倫理を持ち出したのは、正義を持ち出したのは、あんたではないのか、あんたなら、俺を倫理的に攻められるはずではないか。」
「誇りはね、命の事なのよ。一人の人間にたいして、英雄とか不幸な人とか、そういうことをいうのが、最大の侮辱なのよ。ましてや聖女のようにあつかうのなんて、それはあんたが私を侮っている証拠よ。そんな神聖化や同情なんて最大の侮辱なのよ。
倫理も道徳もない。私もね、沢山嫌いな人がいて、なんどもその人達を心の中でのろったわ。貴方だってその一人よ。でもだんだんわかりかけてきたの。」
「それは、俺がいるから、貴方がいるということですか?そういう運命神の事かい?しかしだったら、俺はそんな世界をつくった神を許しはしないよ。」
「さあね、神が憎いなら別に憎んでもいいのよ。ただ私はね、ただ自分の心の暗い所がだんだんと好きになってしまったの。
醜い人、卑怯な人、下劣な人、弱い者いじめをする人。ああ嫌になるわね、反吐が出るわ。そんな人間がもし私の前に立ちふさがるのなら、往復びんた火炎放射器、なんでもいいから、追い払ってやるわ。貴方だってたくさん見てきたでしょう。それに殺しても来たでしょう。
一体どれだけの人が、命が、この世で亡くなったのかしら。それは醜い物だけではないわ。ある一つの美しいもののために、どれだけの美しいものが、生贄にされてきたのかしら。
なぜ世の中に、そんなひどい運命の差があるのかしら。醜いものは、美しいものに嫉妬するわ、羨望するわ。だから争いもなくならないのかしら。それとも、よわかったり、醜くかったりする生き物たちが、生贄にされているせいかしら。
人はみな、いいえ生き物は皆、自分の不完全さがいつか埋まってくれることを、求めているのかもしれない。それが埋まらないから、他者をもとめたり、嫉妬したり、食らったりするのよ。
そんな人間の、生きとし生けるものの、不完全な心、永遠に完全にならない心、穴が開いていて、みな誰かをたよりにして、それを埋めようとしている心、私もその心を、誰かが埋めてくれていると昔はそう思っていた。醜い心、邪悪な心を封印して、否定して、神に祈った。
でもね、今は、この時には、この穴、心にあいた穴こそを大切にしたいとそう思うようになったのよ。もう穴はふさがれなくていいの。ただの強がりかもしれないけどね。そうね私は貴方を憎んでいる。人生そのものも憎んでいる。だったらせめて、あの空や大地をおがむときに、睨み付けるかわりに、少しだけ笑顔で返してやるのよ。だって悔しいじゃない。憎むことは愛することなんていわないわ。ただ私がそうするのよ。」
ここまで言うと妃は目を閉じて話を終えた。エディプスは、彼女に死が訪れるのを、祈りながら待つしかないと感じた。長い沈黙が流れた。
しかし妃は突然目をあけると、ベッドの横の引き出しを指さして、鍵を取り出して、そこを開くように促した。しかも普段や先ほどとは打って変わって、はきはきした様子であった。
「ちょっとまだ話はおわってなかったわ。本当は貴方なんかに見せるのは癪だけど、どうせ誰かに、見られてしまうだろうから、だったら家来たちに見られるよりも、あなたに見られた方が少しはましかもしれない。そこの引き出しを開けてみて。」
エディプスが、引きだしに鍵を差し込みあけると、中には何かが書かれた紙やパピルスの類が大量に入っていた。遺言書かともおもったが、それにしては乱雑な感じだった。
「なんだいこれは? 随分大量だけど。」
「それはね、私が今まで書きとめてきた悪口の束よ。色々と気に入らないことを、そこに書いていたわけ罵詈雑言をね。でも私って優しいイメージでとおっているから、家臣の夢を壊したくないの。まさか自分がこんなにすぐに死んじまうとは思わないじゃない。だから処分し忘れていたのよ。だから貴方に処分しておいてほしいの。
そうそう当然貴方の分も大量にあるのだから、しっかり目を通しておいてね。私やっぱりあなたを愛したことなんて一度もないのよ。ではごきげんよう親殺しの甘えん坊さん。」
妃はそういって、また横になり、しばらくしてから息絶えた。
エディプスは、ずっと泣いていた、自分でも何が悲しいのかわからずに泣いた。もしかしたら、一度も再開できなかった本当の母のためかもしれない。しかし、妃のためかもしれない。彼には自分が泣いている理由が心底わからなかった。
自分が妃だと思い込んでいた女は、それだけの女ではなかった。自分が勝手に妃にしていた女を自分は何も知らなかった。彼女は一体どんな人なのか、自分にはそれがわからないのだ。自分のなかで、勝手に妃を作り上げていただけなのだ。現実は何も見えていなかったのだ。本当に哀れなのは俺自身の心なのだ。それを他人に、気高い人になすりつけてしまった。
スフィンクスの謎、それは人間、しかし今はもうその謎が解けるとは思えなかった。一度といたはずの謎が、なにか得体のしれないものとなってしまった。
そして、エディプスは自分の両目を貫いた。妃が、いや一人の女が死んだ後に両目を貫いた。血がしたたった。黒い血がしたたり、苦痛に悶えた。二度と蘇らない、それどころか永遠に生まれない命の悲しみがあった。
しかし彼は、自分の目をつらぬいたその時から、いやその前に人生最後の光として、彼女の罵詈雑言をちらりと読んだ時から、だんだんと徐々に、おかしな気持ちになって行くのを感じていた。そしてついに心の隙間から、にじみでるように悲しい笑いが込み上げてきた。
「ああ本当だ。俺は何も知らなかった。神も聖女も英雄も、ただの一人の女にくらべたら、なんてちっぽけなんだろう。普通に笑って、泣いて、怒って、意地悪で、残酷で、厚かましくて、立派に生きて、立派に死ぬ。それにくらべたら、神や聖女や英雄や、母親や父親なんてクソくらえだ!
ただの女を聖女扱いにするなんて確かに最大の侮辱なのだ。神や父母なんぞは、一人の女のために売りとばしちまえばいいんだ。実際女ってやつは悪魔だよ。小さなちゃちな小悪魔だ。ヤクザ、ならず者、ちんぴらさ。ああ、結局大地は一週しちゃったなあ、地球は丸いのだ。しかしなんという道化の運命だ。俺は逆さにされて、血を絞られる道化の如く、今頭に血が上っているのだ。
俺はあんたが悲しいのなら、今はもうただそれだけが許せないのだ。でもそれは自分の悲しみをあんたにかぶせているからだ。しかしどっちみちあんたに笑ってほしいのだ。
その真実において俺はいうが、実際あんたはもっと着飾って、笑顔でいるべきだったよ。そうすれば、他の花に見劣りすることなどなかったろうに。いやそうじゃない、あんたが着飾らないからこそ、しかし、これはまた同じことの繰り返しだ・・・」
彼が呪われた運命を悟った時から、王国は再生し始めた。人々は歓喜のあまりに声を上げた。人々の愛すべき日々が、愛すべき人達の笑いが、また戻ってこようとしていた。
それ以降彼は王国から追放され、一人旅にでることにした。盲目の彼は杖をつきながら旅をすることにした。預言者がそう進めてくれたが、これはよげんではなかった。
彼は森へと向かった。盲目となった彼の耳には、波の音が聞こえていた。
それはいきなりやってきて傷口をえぐるが、そのくせ、つかみどころもなくさっていく波。とてもきれいで清らかな波。本当に色々な波が彼の耳に聞こえた。
そして、かつて見たこともなく、彼が引かれもしない波、これからも見る事のないだろう、生まれてこなかった蜃気楼のような波、かすかで、どこかさびしげで、しかしどこか力強く、彼にはなじみがないのに、新たに彼の傷になった波。