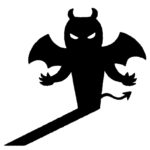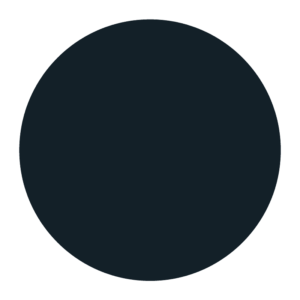
【黒い人にまつわる話】
序文
私が怪談を収集し始めたのは、小学3年生のころからだから、もう40年以上前になる。思い返せば、友達との遊び中に、何か嫌なことがあって、図書館に逃避したのがきっかけだった。
その日の午後の図書館は、妙に人が少なく、もともと薄暗いのも相まって、埃っぽいあの本を見つけた時、誰に見とがめられているわけでもないのに、開く手が震えていたのを覚えている。
それから私は、すすんで色々な怪談を読んだり聞いたりした。しかし、美しい思い出と反対に、現実は色あせていくものだ。年を取るごとに、いつしかあのころのような恐れも感動も感じなくなって行った。
脳科学の発展、幽霊は脳の見せる幻覚だと、そういうしらけが、根底にあるのかもしれない。それとも人間の汚い部分を見すぎたせいであろうか。
だが私は否定したい、霊は幻覚でないとそう直感しているのだ。
故にこの年になって、今までろくに読み物を書いたことのない私が、今まで集めてきた話を加筆修正しながら、まとめてみようと思う。一回目は【黒い人にまつわる話】だ。
似たような話が複数ある場合は、一つだけ選び後は省略した。
推定年月は、事件が起きたと思われる年月を私が推測したものである。
できるだけ、当時読んだままの文章を再現している。
カッコ部分は私の考察である。
Ⅰ.「首を絞める」
推定年月1990年
僕は定期的にある怖い夢を見るんです。
もしかしたら幻覚かも知れないので、夢と言う表現をしているんですけど、実はその時の自分にとっては、まるでリアルな体験なんです。
首を絞められるんです、見えない黒い誰かに、馬乗りになって。その人がやってくるときは、かならず、ごうごうと強い風とか嵐が吹くような感覚になるんです。
その透明な黒い人は、強い力で首を絞めてくるのに、僕は動けなくて、ほとんど抵抗出来ないんです。
息が出来なくて苦しいんですけど、少しだけ耐えるというか、抵抗していると、そのうちに目が覚めて、なんとか窒息はしないんです。
でも、そういう夜は、少しうとうとするたびに、その人が襲ってくるんです。何度も何度も。夢が覚めるとまた夢の中にいるみたいに。
それがもう10年以上です。
(いきなり幻覚や精神病質めいた話ではあるが、若いころの私にはこういった話も興味深かった。90年代はまだインターネットも発達しておらず、金縛りと言う現象の解説も本を読まねばならなかった。もっとも金縛りも、身体的なものと、霊的なもの、に分類できるというのが私の持論であるが)
Ⅱ.「都会の黒い人」
推定年月1960年以降
俺はまだ小さいころから、田舎の排他的な雰囲気にうんざりして都会に一抹の憧れを抱いていたのだが、実際に引っ越してみると、こっちも迷信深くないことだけが救いなぐらいで、いやその表面が変わっただけで、人間なんてものは、どこでも変な枷に縛られていやがると狭い了見で納得してしまった。みんな自分で自分の身を焼いて、苦しんでいるふりをして、内心喜んでいるのだと。
隅のほうではどこでも、貧乏な男が女房のわずかな稼ぎをむしり取って大酒博打の放蕩した挙句、水商売とか見世物小屋の女と一緒になって傷をなめ合って、泣き崩れてなんて具合なのだ。
どころか、ここには、山に吹く風やトンボの群れがいない。収穫期の稲穂の黄金の輝きもない。功利主義の巣窟。ご自慢のビルディングは、精神の墓標に過ぎない。
前置きが長くなったが、これからの話も、ある意味では大差ない。この都会にやつらがいたことが、俺を最も失望させ、同時に歓喜させた。
それは黒い影だ。そいつが田舎の山には一匹。しかしこの街には沢山いた。
地元では、鬼さんと呼ばれていたやつで、田舎の老人によると、死体に乗り移って死者の生前の恨みをはらさせる鬼だとか、昔退治された妖怪の亡霊だとか、そいつに影をふまれた人間は、大けがをしたり死んだりするとか、その様に言われていた。
ようするに、ただ子供を寝かしつけるための作り話の類なのだが、俺にだけ、とにかくそれらしい影が幼少期から見えていたのだった。ただそいつは山のある場所以外では見かけなかったので、老人共が言っていた幽霊と同じかわからない。
俺はそいつに自分から話しかけたことはない。臆病な俺には、陰で嘲笑う事しかできない。
昔一度だけあいつが、何かしようとしてきたことがある。ある薄暗い夕方に皆で、「だるまさんがのろんだ」をやっていた時に、あいつは現れた。俺が鬼の時、あいつは混ざっていた。でも薄暗いせいか誰も気が付かない。
「だるまさんがころんだ」俺が振り返るたびに、あいつはへんてこなポーズで、近づいてきた。
俺はその時は不思議と怖くなかった。だんだんとやつは近づき、ついにこちらのすぐ目の前まできていた。他のやつらは全員つかまって、俺の近くにいた。みんな近くにいるのに、そいつが見えているはずなのに、終わらない。
「だるまさんがころんだ」
俺は怖かった。子どもの頃にみた幻覚、そういう類のものが俺の脳裏に焼き付いていて、それは現実にあったことなのか、ちがうのか、それが今でもわからないのだ。人に聞けば、そんなことはないと、否定されるが、俺にはどうも判別がつかない。
この街には、その影が、幼いころに何度も見たはずの黒い人が、大勢いる。田舎では一匹だったはずだ。たとえば、駅のホームに人ごみに交じって何人もいるのだ。
おれは出来るだけ無視した。あいつらに関わったら、きっと生きてはおれないと思ったんだ。死にたくなかった。
ずっと、自分が自分であることに不快だったくせに。もしできる事なら、自分で、自分の首を切り落として、その首にキスしたいと思っていた。それが出来ないなら、自分で自分を笑ってやるのだ。いやそれもまた不快だったんだ。人生はただ不快と退屈、そしてぬぐいようのない、いわれのない罪悪感の中に過ぎていったのだ。
あるとき、やつらが大量に列をなして、集まっているのを見かけた。
もしかして、誰かが死んだのかと思って、わくわくしながら、おれは列をたどった。そうしたら、そこは葬式会場でも墓でもない、ただの路地だった。暗い路地に陰の人が列をなしている。俺はすぐに逃げ出したよ、あれからは逃げる事しかできないのだ。
でも最近、やっと決心がついたような気がしている。あの路地にはなにがあるのか、あの黒い人たちは何者なのか、次は確かめたいと思う。
(この話は、大学生の時に、ある図書館で読んだ本にのっていた話だ。実はその本は寄贈されたもので、しかもただでもらいうけることが出来た。ゆえに本文はその時のままだ。田舎の黒い人が都会にもいるというのが、黒い人の正体を暴くカギになりそうだ。ところで、この話でひっかかるのは体験者のその後だ。もし黒い人が幽霊だったのなら、彼はどうなったのであろうか?)
Ⅲ.「山の黒鬼」
推定年月2000年以降
これは、俺の田舎で体験した出来事。
田舎は、過疎地域と言うか、限界集落というか、とにかく自然が豊かな所だった。人間よりもイノシイの数の方が多かったとでもいえば、それっぽくなるかな。いや単純に田んぼと山ばっか。
都会から出たことがない人は、知らないだろうけど、現代日本にも、普通に山間集落があったりするんだよ。
村にはある言い伝えがあって、といっても夏の肝試しの前に聞いたやつだけど、なんでも、村の祭りの日に近くの山の祠に行くと、黒鬼が出るというんだよ。
なんでも昔、この一帯で暴れていた盗賊だか妖怪で、人の生き血が好物だったらしい。それを退治したのがこの村の若者だったから、そのお祝いのお祭りなんだと。
まあいったわけ。中3の時にしかも彼女と2人で。田舎はのどかだけど、同調圧力は過剰だから、どうにも暑苦しくてね。って嘘にきまってんじゃん、そりゃあカップルでイチャイチャするのに丁度いいからよ。
祭りの当日、彼女の浴衣姿がまぶしくて、まだ火がついていないのに、彼女の目も肌も燃えているようだった。彼女のほうも、「絶滅した日本狼がこんなところにいたのね」なんいたずらそうに笑うんだ。
皆がやぐらの周りを円形におどってる祭り会場を抜け出してさ、その祠に向かったのはいいけれど、なぜか辿り着かない。祠はそんなに遠くないし、一応懐中電灯もあるから楽勝なはずだった。
体感30分どころか、1時間歩いてもたどり着けないんだよ。あのころは、携帯なんかまだ普及してないから、ポケベルはあったけどね。結局なんとか祠に辿りつくことが出来たんだけど。
でも変だったんだよ。その時祠の前に2本ろうそくが立っていて、火が燃えていたんだ。というか、火が見えたから場所を見つけられたんだけど、普段は火なんか焚かれていないはず。祭りだからかとも思ったんだけど。
二人ともその時妙な事に気がついて少し寒くなったんだ。そもそも鬼を倒した祭りなら、祠でやればいいのに、なんで違う場所でやっているのか、ってね。俺達は少し離れたところから祠を見て固まってしまった。
だけどさ、彼女が一緒じゃあ、ビビリな所も魅せられないし、祠に近づいてみようとしたんだ。その時、俺達がいる所から、右手のほうの獣道からやってくる何者かの影が見えたんだ。
俺達は一瞬ビビッて、枝の影に隠れたんだ。まさか黒鬼を警戒していたわけではないんだけど。でもそれはもっと異様な何かだったんだ。
そいつは、全身真っ白だった。頭の大きい白い棒人間。いや思い出すと、ただの白い塊だったかもしれない。そいつが、祠の前にぴたりと止まったんだ。
それで終わればよかったんだけど、そいつは振り返って、息を殺して隠れていた俺達のほうをじーっと見つめたんだよ。顔なんかないのに、そいつは目で俺達を見ているんだ。
俺達は悲鳴を上げて必死に山を下りようとした。さっきまで見えなかった、祭りの火がその時は見えたんだ。でもそいつも追いかけてきて、山道なのにすごく早くて、根っこにけつまずいてさ、途中で追いつかれたんだ。
俺は彼女を守るために抵抗しよとしたけど、実際には、うわああああとか叫ぼうとした声すらかすれて、足はがくがくで、その場にへたり込んで、ようするにビビって何もできなかったんだ。
その白い人は、俺をつかもうとしてきた。もうだめだと観念したよ。そうしたらさ、彼女が前に出て、俺の盾になってくれたんだ。彼女もたぶん震えていたと思う。でも、俺を守ろうとしてくれたんだ。
その後どうなったのかは、かなりうろ覚えなんだ。気がついたら、二人とも田んぼの中で、泥だらけで、寝転んでいたんだ。たしか彼女が白い人に触られた気がしたんだけど。
その後も俺達は別れなかった。あんなもん見たら、誰でもビビるのは当然だと、彼女は笑っていた。
俺はさ、今でいうドキュンと言うか、正直に言うと、女のことを馬鹿にしていたんだよ。やっぱさ、力のある男が社会をリードするというか。女なんてのは、力のある男に媚びるだけのやつらだなんて思っていたんだ。
でも、あの時の彼女は本当に強かった。いやたぶんそういう言い方も失礼なぐらい。なんだろうねこの感じ。俺は彼女を、男としてこんなことを言うのは、カマ野郎的で格好悪いのかもしれないけど、正直に言うと、いややっぱり言葉では表せないんだ。ただ今風に言うと尊いって感じかな。
一応、真相と言うか、後日談なんだけど、あの祠の話を、結構長生きな婆さんに聞いてみたんだ。そうしたら、あの祠は、黒鬼を退治した記念ではなくて、なんか飢饉的な物で、大量に人が死んだことがあって、その鎮魂のための物なんだって。だから、祭りとは関係ないんだとよ。
それが黒鬼と関係していると言われているのは、飢饉のときの間引きとか食人とかの歴史を隠すためなんだってさ。これも本当の話かは分からないんだけど。
ただその時彼女が言った一言が気にかかって
「もしかして、水子、それか堕胎された子供かも」だってさ。どちらにしても、白いやつの正体はわからなかった。
でもまだ後日談と言うか、続きがあるんだ。俺達その後都会に出て結婚したんだけど、彼女死んじまったんだ。見ず知らずの婆さんを助けて、身代りにトラックにひかれたんだ。
俺は、葬式の時、また不思議な気分になった。彼女は、また自分を犠牲にして他人を守ったんだ。
やっぱり彼女はいいやつなんだ。おれは、こんなこと言うのは恥ずかしいけど、彼女を神聖だとおもったんだ。あの時と一緒だ。いや恥ずかしくない、やっぱり彼女は神聖だったんだ、それは誇りに賭けて誓うよ。
でも俺はさあ、その後くるっちまったよ。
ある時、おれは地獄の絵を見たんだ。それは針の山とか、血の池地獄とか。地獄では、死者が鬼に何度も痛めつけられるんだ。たとえ体が裂けても、すぐに再生するんだ。
俺はあの彼女が人をかばった時、本当に神聖な気持ちになったんだ。この世界でこれほど偉大な存在はない、仏でも神でも裸足で逃げ出すよ。
でも地獄の本を見た時、あの時とは、あの時には決して、わかなかった感情、思いがこみあげてきたんだ。結局黒鬼はいたんだ。
(この話は、ある怪談投稿サイトで見つけたものだ。具体的な地域はぼかされていた。)
Ⅳ.「外国の民話」
推定年月1500年代
この話は、私が大学のゼミで民俗学を研究していた時によんだものだ。あのころは忙しかったし、資料も英語なので、若干うろ覚えなのだが、たしかフィリピンの話だったと記憶している。
ある田舎の村で、女性が氏神を祀る祭壇にお参りをしていたところ、木々の影から、黒い人が二人こちらを見ていた。見られていることに気が付いた黒い人は、彼女の周りを一人は、時計回りに、もう一人は反時計周りにくるくると踊るような足取りで回ったそうだ。
その時その女性には、虹色の光が見えたという。
(この話単体ではどうと言うこともないが、いうまでもなくⅢとリンクしているように見えることから、ここに収めた。しかしそうなると、場所と時間が合わない)
Ⅴ.「街灯下の黒い人」
推定年月2000年以降
実は恥を忍んで書くが、この話はあるゴミ捨て場で拾ったノートに書かれていたものだ。私は小さいころ貧しかったせいか、こういう変な性分がある。
ただこの話は、確実に創作というか、創作ノートであろうと思う。それは本文を見れば一目瞭然だ。しかしえり好みはしないで、収録して行こうと思う。
これは、俺が大学に入学して、アパートに住みはじめた時の話です。
入学して最初の1か月は、コンパとか友達作りとか、他にも色々な準備があって、気が付かなかったんですけど、生活にも慣れてきたころ、深夜に怪しい男を見かけることに気が付いたんです。
俺の住んでいた部屋のベッドの横の窓は、道路に面していてそこには街灯が1本立っていました。だから雨戸を閉めないと寝つきが悪いんだけど、でも俺は開放的な雰囲気が好きで、よく開けて寝ていました。
ある時、その街灯の下を覗くと、背の高い男、それも黒い影というか、そういう何者かが佇んでいたんです。その男は電話でもしているように、背中を丸めてうつむいているから顔は見えないですけど。
その時は、一時的にぎょっとしましたが、でも別に気にしないようにしました。人には人の事情があると思うようにしたんです。それに俺も身長180の男ですから。
ただそれでも、まさか、それが毎日続くとさすがに、きみが悪いを通り越して、怖くなりました。その男は気が付くと夜同じ時間の、同じ場所に佇んでいるんです。あいかわらず、うつむいて顔は見えないのに、じっとこちらを見ているような気さえするんです。
友達に相談しようとも思いましたが、でもまだ1年前期で、こんなオカルトな相談できる友達もいなくて、やはり最初の印象は大切にしたいですから。今の科学万能の世の中に、本気で幽霊騒ぎをするというのもねえ。そういうのは、もっと仲良くなった後にネタでやるものだと思うんです。
だからしばらく一人で怯えていたんですけど、別に何も起きなくて、ただただ男は佇んでいるだけ、きがつくと消えている。
たまに不安になって、盗聴器とか探したりしましたけど、だんだん慣れていったんです。
そもそも、俺がすんでいたアパートは、奥まったところにあるというか、大学から遠くないのに、家賃も安くて、暮らしやすい穴場だったので、多少のリスクには目をつぶることにしました。というよりも、その頃は大学生活に慣れるのに必死で、そのほかのことは、意識的に無意識化していたんです。
特に、教養科目の数学の教授が無理難題を吹っかけてくる人で、俺は受験組なのでまだましでしたが、指定校推薦組は、相当苦労していました。
大学生活、課題やテスト対策、と言う口実の友達同士の交流、図書館でみんなで調べものをしたり、カラオケにいったり、ラーメンを食べたり、そういうことが忙しかったんです。
俺は、結構実験が得意だったので、そのレポートを創る時には、その担当になることが多く、その他の資料を横流ししてもらっていました。
ところで、少し中断してこれから全然関係ない話を書こうと思います。
俺は、高校の時受験勉強に苦労していました。ただ出世のための手段である無機質な勉強に嫌気がさしていたんです。
どんなに勉強して、人を蹴落として、高い地位についても、長い労働の果てに、人生最後は死んで終わりだと。
そんな時、世界はいくつかのレベルの次元に分かれているとか、魂の転生だとか、生命の樹だとか、そういうオカルト方向に憩いの場を求めて、なんとか人生の無意味感から、逃れていました。
勿論それは遊びのようなものです。自分もどこか、この次元とは異なる、精神世界にいけたらいいなと、そう漠然と考えていたりしました。こういうオカルト的な部分があることがコンプレックスでもあり、自分だけの秘密として、楽しくもありました。
しかしある時顕微鏡をとおして物を見ている時に、それは自分が普段見ている世界と全く違う物であることを意識しました。もしかしたら、あのオカルトで言っていた、異なる世界とはこのことかもしれない。どこかまったく違う空間に、別に世界があるのではなくて、人間は認識をかえることで、別の世界にいけるのではと、そう思ったんです。
でもやはり、それはおかしい。どんなに物を分解しても、別の世界に行けるとは思えない。勘違いしないでいただきたいのは、俺が見たあの男が、別の世界の人間だなんて、言う気はないのです。それに俺の心の闇とか、幻想の類でもないと思います。
ただ、もしありえるなら、誰も犠牲にならない世界に行ってみたい。際限のない争いで、世の中が発展するなんて、おかしい。それに何の価値があるのか。俺は10代の頃実はそればかり考えていた気がします。
俺は、そういう無駄な事ばかり考えていたせいで、社会人として、まったく人後を排することになりました。しかも、愚かにもそれに気が付かずに、自分だけが真実を探求しているつもりだったのです。
それに気が付いた時には、青春は潰えており、自分の愚かさに絶望し、世の中を恨みました。俺は、実際の生活ではまったくの役立たずだったのみならず、知的に言っても生来3流の人間なのです。
なぜこうなってしまったのか。俺は自分の意思を批判しました。世の中を恨むか、自分の意思を批判するか、その2択しかなかったのです。
自由意志の追及が、自分の課題になりました。なんのことはない、また世の中から背を向けたわけです。世の中が悪いのか、私が悪いのか、その真実にすがりたかったのです。
そして「私とは何か?」という問題に多くの時間を費やしました。
しかし、言うまでもなく、知的に3流、つまり生来愚鈍な私に、そのような高等な学問は難しいものでした。昔何かの小説の登場人物が、ユークリッド幾何学が自分の知力の限界だと言っていましたが、私にはそれすら難しかったのです。
しかし労働の責め苦さえなければとも、今となっては思うのです。
私という生来惰弱な人間には、知力も体力も気概もなく、1日の労働をした後には、もう何もする気がおきなかったのです。病気と言えないような慢性的な不調がかさなり、疲れた体や精神を回復することすらままならなかった。
しかし、私は、私なりの答えを探し求めました。そして「私とは何か?」の問題は、「何が私であるのか?」の問題へと変わっていきました。
長年多くの迫害と犠牲を見てきて、いや私自身がその当事者として。それは世の中の知恵者達が言うようなものではない。高慢ちきなやつらは言うでしょう。
「貧乏人は箒で人間社会から掃き出されちまう」だとか、「賢者は歴史に学ぶ、愚者は」だとか、「小説家は弱者の生活を隅々まで予言して描ける」だとか。
そういうことは、いくらでもいえますよ。言うだけならね。だってかれらは賢いのですから。生まれつき賢いお頭を神様からもらっているのですからね。
やつらは、ただの恵まれた馬鹿者ですよ。なんていったって、その口で正義だの努力だの愛だのと、正論とやらを唱えるんですから。
私たちの体験するのは、そういう思い上がったものではないのです。
ただ、自分の愚かさ位は知っているというのが、拠り所なのです。それをまさに今体験し生きているということが、私たちの拠り所なのです。
ある日俺はかなり遅く深夜の道を、一人帰路についていました。
打ち解けた友と、俺にしては珍しく酒を飲んでふらふらといい気分でした。彼らとなら、街灯下の男の話をネタにして、みんなで盛り上がれるかな?なんて考えていました。
細くて暗いコンクリート道にさしかかった時、前方に例の男が立っていました。あいかわらずうつむいて顔は見えない。いつもは、街灯の下にいるのに、どうして。
俺は彼に近づきました。さすがに鼓動が早くなっていることに気が付きました。まるで心臓の音と地面をける音と時間が全て一体になったような。
でも、もう少しで彼の顔が見えそうな位置に来た時に、携帯がなったんです。俺は友達かと思い、急いで出ました。
「・・・・・・ハイラナイデモラエマス?」
音だ。着信は家から。フレッツ光のお姉さんに載せられて光電話契約しちゃったんだよな。誰もいるはずがないのに、友達からのドッキリかなあ。いや彼からだろうなあ。
今のこの状況、背の高い男が電話をかけてうつむく、目の前の街灯下の男と全く同じだ。目をあげると、いるのだろうか。