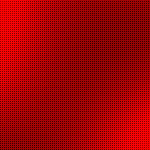ある病院の待合室で50代の男性XとYはばったり出くわした。元々仲の悪くない二人であったが、このころは疎遠になっており、長い待ち時間中の暇つぶしと、絆を確かめ合う意味でもお互いに色々な話を始め、そしてなぜかそれは不謹慎にも怪談話にまで発展した。
「ある友人の話なんですけどね。彼がした不思議な体験で、しかもある意味では現在進行形なんですよ。」
「どういう話なんです?」
「話は彼が小学生のころからなんですがね、よくある学校の怪談で看護婦に追いかけられるという話があるのをご存知ですか?」
「ああ、そういえばそんな話があったような。たしか夜の学校に台車を押した看護婦が出没して、生徒が追いかけられてトイレに逃げ込むやつですよね」
「そうです。友人はそれを目撃したんですよ」
「夜の学校に忍び込んだのですか!?」
「昔は今よりも自由な昭和の頃の話ですからね」
「たしかに、あのころは我々もヤンチャしてましたねえ」
「宿題を取りに行ったとかではなくて、別の怪談疑惑があって度胸試しに仲間たち数人で肝試しに行くことにしたんです。でも皆当日になると理由をつけて、彼以外だれも来なかったんです」
「それで一人で入ったんですね」
「そうです。それで例の看護婦に出くわしたんです。3階の校舎にいた時に、暗闇の中から、車を押す音がして、ぎくりとして、廊下の先を見ると、その女が台車を引いて、近づいてきたんです。そして追いかけてきたんです」
「それで、どうしたんですか?」
「お決まりのことを言うとね、彼は恐怖して、ビビッて逃げましたよ」
「やはりトイレですか。個室に入ると一つ一つ扉を確認してきて、『ここにもいなーい』と言いながら、最後に主人公のところに来て、『みーつけた』というやつですか?」
「いえ、トイレには逃げなかったんです。彼は2階の教室の一つに逃げんたんです。1階まで下りて、外に逃げればよかったのに、気が動転していたのでしょう」
「それで、逃げられたんですか?」
「彼は教室の窓からベランダに出ました。なぜかドアが開いており、そこにいれば安全だと思ったそうです」
「セオリーは外してますねえ」
「それでしばらくベランダに、下を向いて、耳をふさいで、体を縮めて、うずくまっていても、特に何かが、おこるわけでもなかったので、これはもう振り切ったな、と思ったのだそうです。第一台車をおして、階段を降りられるわけもないしと。それで顔を上げたんです」
「で、いたんですね?」
「はい、やっぱりいたんです。」
「どこにですか?」
「2階なので3階のベランダの壁が上にあるんですよね。そこから逆さになって、女が彼を笑いながら見下ろしていたそうです。『みーつけた』たっね」
「上からですか、看護婦が。しかしそれでは見下ろしているのか、見上げているのかわかりませんね」
「看護婦というよりもその顔は蛇が女の髪とナースキャップをかぶっている様だったんだそうです。とにかく顔が蛇のようなんです。長い舌をだしてねえ」
「へえ蛇ですか、それは意味深ですねえ。じゃあその友人はカエルの気分だったでしょう。その後はどうなったんですか?」
「いえね、それから先はよく覚えていない、という例のやつなんですよ。気が付いたら、当直の先生に、しがみついていたらしいです」
「はあ当直の先生がいたんですね」
「その直後は何もなしです。ただこの話は今でも続いているんですよ」
「まさか夜な夜な化けて出るんですか?」
「次の場面はそれから10年以上後、友人が道路で事故をおこして、その時怪我をして緊急手術が行われることになったんです。その時に意識不明の彼の横で彼の名前を呼びかけていた看護婦さんがいたんですが」
「それってもしかして」
「ええ、それが蛇の看護婦だったんですよ」
「いやでも、顔が蛇の人間なんているわけがないし、オカルトではレプティリアンとかいうのがいるとか言いますけど」
「顔が蛇というのは正しくはありません。ヘビのような女、だと言えばいいですかね。私も何回か、あっているので」
「あっているんですか、でもどうして、その後どうなったんですか?」
「その看護婦ですが、彼はその人と手術の後に打ち解けて、結婚してしまったんですよ」
「へえ、しかしよく蛇のような女と結婚なんかしましたね。容姿的にもあまり良いとは思えないけれど、いやこれは湿原だったかな」
「それがかなりの美人なんですよ。人ごみとかにいても、そこだけ光がさしている、ような、はっとさせられる美人です。後光が差していて自信にあふれていると言ってもいいでしょう」
「そうなんですか・・・羨ましい。しかしそれならハッピーエンドですね。一応何かの運命なんですかね?」
「わかりません。彼女からは雰囲気というか、なにか冷酷な感じを受けます。今では私も友人なので、こう言ったら悪いのですがね。しかし彼にたいする束縛は大分きついようですよ」
「ははは、しかし正直に言うと」
「正直に言うと?」
「いやあ、最近オカルト本を家内がはまってしまって、蛇関係の話と言えば、ありがちだなと思いまして。キリスト教とか中国の神話とかにも蛇は出てくるでしょう。良い悪いはあるけれど、人類の創造に関わる存在だ。あとは人魚姫とかもありますが、あれも下半身が人間ではない長いものだという意味では似通っていますね。だから蛇と女をむすびつけるのはいまさら面白みのない気がしてねえ」
「そうですねえ。女性は蛇皮が好きだったりしますしねえ。私も少し安直だと思うんですよ。もしかしたら友人の作り話なのかもしれません。あの女を見れば誰でも、蛇、を思い浮かべるかはともかく、私には、蛇、と言われて納得してしまいましたが」
「まあいいんじゃないですか。ただしいて言うのなら、多分人魚姫とかもそうですけど、女性の下半身が蛇なのであって、上半身は美女であってほしいと私は思うから、その話は、少し嫌な気持ちになりますけどね」
「しかし絶世の美女ですよ。上の如く下も然りともいいますし」
「ははは、しかしきわめて正常な感覚あるいは世間的なイメージで言えば、女性を蛇と結びつけるのは何ら根拠のない宗教的な偏見でしょう。道に迷った坊さんが、自分のよこしま心を女にかぶせたんですよ。釈迦ですらむっつりスケベの女嫌いだったらしいですからねえ。彼が悟ったなんて嘘ですよ。男に悟りが開けるはずがない。しかし、だんだんオカルトが行きすぎているようですしこの話はこれでやめましょう」
その時丁度、片方を呼ぶ看護師の声がした。
「ああ、今私は呼ばれたようです。しかし、男に呼ばれるとはねえ。私も美女がよかったのだけどねえ」
「いけませんよ。最近はそういう発言は、あっという間に社会的地位を失いかねない。ただでさえ、貴方は古めかしいタイプなんだから」
「まあそうですねえ。部下にもよく言われますよ。しかし、散々蛇女の話をした後でそれをいってもねえ。じゃあお先に失礼、もし時間が合えば、そのうち一杯行きましょうや」
「そうですねぜひに」
―――――
もう片方は話し相手がいなくなり、仕方なく病院においてあるまったく興味もない健康関係の雑誌を無意識的に手に取ろうとした。だがそれはうまくいかなかった。他の存在が視界に入り込み、彼はそれを見上げた。それは知り合いのZだった。
「やあZさん。お仕事順調ですかな?」
「やあこちらはなんとも皆頑固でね。貴方のほうは今もさっそく一人送り出したようですね」
「ええ面白い話ができましたよ」
「しかしこの仕事を始める前は、こんなにあちら側に旅立つ人が多いなんて、思いませんでしたねえ」
「まったくです。日本はともかく、世界的に見れば人口は20世紀初頭の数倍に増加していますからね」
「しかし私のところは大きな病院でして、顧客も多いのですが、貴方はこの朽ち果てた病院で、どうやって顧客をあつめているのですか?」
「ああ、それはね、病院にはどうしても、自分がこちら側にいられない存在だと気が付かない人達がいるのですよね。そういう人を旅立たせるのが貴方の仕事です。でも誰もが病院や自宅で旅立てるわけではなく、体がなくなってから、ふとした時にはじめて、実感できるそういう人もいるんですよ。だからそういう人を、この廃病院でお世話しているということです。私はこの町には知り合いが多いし、それにあとは口八丁ですよ」
「ははあ、そんなもんですかね。でもねえ私がいくらあんたはもうこの世界にはいられないといっても、顧客は全然納得しないんですよ」
「その方法もいいですがねえ、私は人には向き不向きがあって、自分が納得できなくても、なんとなく気が付いたら消えているというそういうあり方もいいのではないかと思いますね。ようは本人が苦しまなければいいのだと思うのです」
「そんなもんですかねえ」
「もちろん、本人が自覚しているということも大切かもしれませんが、人ぞれぞれでしょうねえ。私だって、まだ納得していないからこうしてこの仕事をしているのだし。それに良い仲間たちもいますからねえ」
丁度、診察室から一人の看護師がでてきた。
「お二人さん、お話もいいけれどまたナイルちゃんが新しい顧客を連れてきたようですよ」
「ああ、そうだねえ」
「ナイルちゃんですか?そういえば何か鈴のような音が近づいてくるようですが」
「猫ですよ。いつも顧客を連れてきてくれるんです」
「ははあ、こういう相棒がいるからなんですね貴方の仕事がはかどるのは。私もこちらに越してこようかなあ」